- スタッフブログ
- ホーム
歯列矯正に抜歯は本当に必要?判断基準と医師の考え方を解説
皆さん、歯列矯正をご検討されている中で「抜歯が必要になるかもしれない」と聞いて、不安になったことはありませんか?特にお子さまの矯正や成人矯正を検討されている方にとって、健康な歯を抜くことには大きな抵抗があるものです。しかし、抜歯はすべての矯正治療で必要なわけではありません。
そこで本コラムでは、「歯列矯正における抜歯の必要性」について、歯科医師の視点から詳しくご説明します。判断の基準や、抜歯が不要なケースについても丁寧に解説いたしますので、安心してご参考ください。
▼歯列矯正の抜歯とは?
歯列矯正における「抜歯」は、虫歯や歯周病によって自然に悪くなった歯を抜く治療とは異なり、「便宜抜歯」と呼ばれる目的で行われます。これは、歯並びを整えたり噛み合わせを調整したりするために、健全な歯を計画的に抜歯する方法です。
◎便宜抜歯の目的
便宜抜歯の主な目的は、「歯を並べるスペースを確保する」ことです。日本人は比較的顎のサイズが小さく、永久歯がきちんと並ぶだけのスペースが不足していることが多くあります。そのため、歯が重なって生えている、前歯が前方に突出した「出っ歯」、奥歯が内側に傾いた「叢生(そうせい)」などの症状が見られることがあります。
このような歯列不正に対して、顎を広げるか、歯を抜いてスペースを作るかの判断が必要になります。便宜抜歯は、歯を動かすスペースが十分にない場合や、骨格的に制限がある場合に選択される治療方針の一つです。
▼歯列矯正で抜歯が必要なケース
以下のようなケースでは、歯列矯正で抜歯が必要となりやすいです。
1.顎の骨が小さくてスペースが足りない
歯列矯正で抜歯が必要になる最も一般的なケースが、「顎の骨が小さくて歯が並ぶスペースが足りない」状態です。日本人は欧米人に比べて顎が小さく、永久歯が並びきらずに重なり合って生えてしまうことがよくあります。このような状態を「叢生(そうせい)」と呼びます。
顎の成長が終わった成人の場合、スペースを確保するために歯列を大きく拡げることが難しく、無理に非抜歯で治療を行うと、歯列が外側に突出し、歯茎から歯根が飛び出す「骨外移動」や、噛み合わせの異常、歯茎の退縮を招くおそれがあります。さらに、歯が重なっていると歯みがきがしにくくなり、虫歯や歯周病のリスクも高まります。
このような場合、便宜抜歯により必要なスペースを確保することで、歯を正しく配列し、清掃性や審美性、そして咬合バランスを整えることが可能になります。
2.歯のサイズが大きい・多いことでスペースが足りない
一見すると顎の大きさは標準的に見えても、歯自体が大きかったり、本来生えるべきでない歯(過剰歯)が存在したりすることで、スペース不足に陥ることがあります。このようなケースも、歯列矯正の中で抜歯が必要とされる典型例のひとつです。
特に、歯の幅径が平均よりも広い方は、同じ顎の大きさでも歯が収まりきらず、叢生や出っ歯といった歯列不正を招きやすくなります。矯正においては、このスペースの問題を解消するために、第一小臼歯などの便宜抜歯が行われることがあります。
また、過剰歯や乳歯の早期脱落によって周囲の歯が寄ってしまっている場合も、歯列の調整には抜歯を伴うスペース確保が必要になることがあります。こうした判断は、歯と顎の比率(アーチレングスディスクレパンシー)を精密に測定し、全体の咬合計画を立てる中で行われます。
3.上下の噛み合わせが極端に悪い
噛み合わせ(咬合)の不調和が強い場合、単に歯並びを整えるだけでは機能的な改善が難しいことがあります。特に「過蓋咬合(かがいこうごう)」や「開咬(かいこう)」、「交叉咬合(こうさこうごう)」など、上下の歯列が正常な位置で噛み合っていない場合には、抜歯を含めた積極的な歯列の再構築が必要になることがあります。
たとえば過蓋咬合では、上の前歯が下の前歯を深く覆い隠すことで、下顎の運動が妨げられ、顎関節症のリスクや咀嚼機能の低下を招く可能性があります。歯列矯正では、この咬合の深さを調整するために、歯を上下方向だけでなく前後にも移動させる必要があり、そのスペースを得る手段として抜歯が有効なことがあります。
矯正治療では、噛み合わせの改善によって顎の負担を軽減し、発音や咀嚼といった機能の正常化を図ることも重要な目的のひとつです。そのため、歯列全体のバランスを見たときに、抜歯が最も適切と判断されることがあります。
4.重度の出っ歯や受け口
「出っ歯(上顎前突)」や「受け口(下顎前突)」などの前後的な骨格のズレが大きいケースでは、見た目だけでなく、口元の機能や健康にも悪影響が及びます。たとえば出っ歯では、口が閉じにくくなることで口呼吸の習慣が付きやすく、虫歯や歯茎の炎症を引き起こしやすくなります。また、前歯の突出により、外傷を受けやすくなるというリスクもあります。
このような場合、前歯を後方に移動させて口元を整える必要がありますが、そのスペースが不足していると治療効果が十分に得られません。そこで第一小臼歯などの便宜抜歯を行い、歯を引っ込めるためのスペースを確保するという処置が選択されます。
受け口の場合も、骨格的に下顎が前方に突出していると、外科的矯正(顎の手術)が必要となることがあります。その際にも、術前矯正として抜歯を含む治療が組み込まれることが一般的です。
▼歯列矯正で抜歯が必要ないケース
次のケースでは、歯列矯正で抜歯が不調となりやすいです。
-
顎と歯のバランスがとれている場合
もともと歯列に並ぶスペースが確保されている方や、わずかな歯の重なりだけが見られる方の場合、抜歯は不要です。マウスピース矯正や軽度なワイヤー矯正で十分に改善可能なケースもあります。
-
成長期のお子さまの矯正(第1期治療)
子供の矯正では、成長に合わせて顎を拡大する「拡大床」や「急速拡大装置」などを使用し、歯が並ぶスペースを確保できることがあります。このような装置を使って顎の成長をうまく誘導することで、永久歯が正しい位置に並びやすくなり、将来的に抜歯を避けられる可能性が高まります。
-
歯を後ろに動かすスペースが十分にある場合
たとえば、親知らずをすでに抜歯しており、奥歯の後方移動が可能な症例や、もともと奥歯が少ない場合などには、抜歯をせずに矯正できるケースも存在します。こうしたケースでは、歯を後方に動かすことで、前歯の突出を改善できます。
-
歯列の幅を拡大できる場合
歯の傾きを調整したり、アーチフォームを広げたりすることで歯を並べられることもあります。無理に抜歯をせず、歯列の幅を広げて調和を取る方法は、特に軽度から中等度の叢生に適応されることが多いです。
▼まとめ
歯列矯正において「抜歯が必要かどうか」は、患者さま一人ひとりの歯並びや顎のバランス、年齢、骨格的要因などを慎重に診断した上で決定されます。必ずしもすべての矯正において抜歯が必要なわけではなく、成長期のお子さまや軽度の症例では、非抜歯で対応できるケースも多くあります。不安な方は、歯科医師にじっくり相談のうえ、治療方針を確認されることをおすすめします。
Copyright © KAGOSHIMA CENTRAL CLINIC All Rights Reserved. platform by
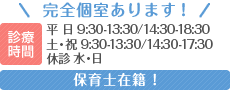
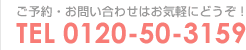
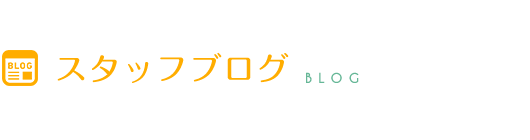
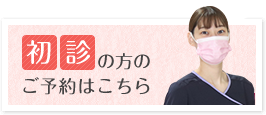
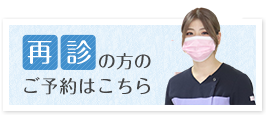


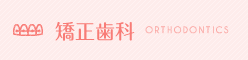

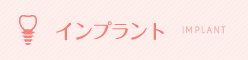
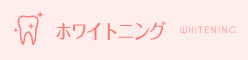
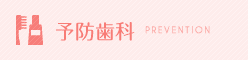

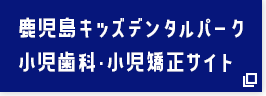
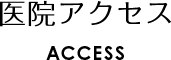
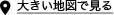
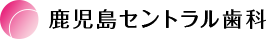
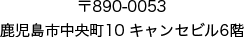
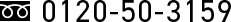
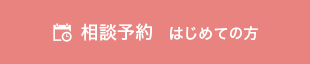
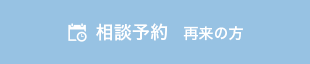
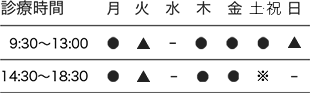
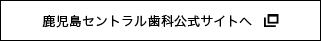
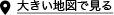
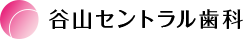
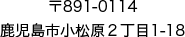
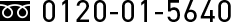
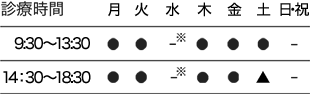
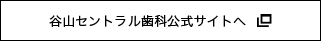
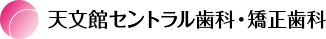
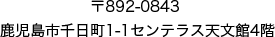
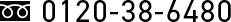
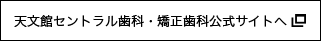
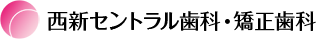
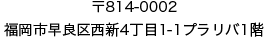
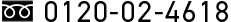
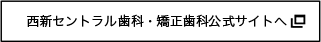
2025年4月25日 (金)
カテゴリー: 矯正歯科